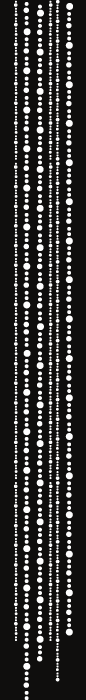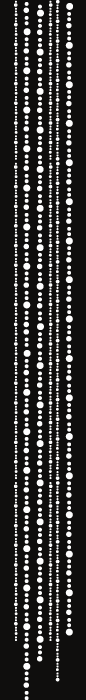
紫ベビードールはバーレスクの殿堂にして世界大会である「ミス・エキゾチックワールド」で優勝しながらも、厳密な意味ではバーレスクではないと定義されることがあった。ビバーチェは、表面的な定義にこだわることよりも、バーレスクって何だろう?と深く考えるようになっていく。そこには、彼女自身が抱えていた欠点をも受け入れてくれる不思議な魅力があった。
ダンサーにとって太りやすいことは致命的であるという見方があります。私もその通りだと思っていました。それと、キャラクター的に「笑われやすい」というのも、シリアスなダンスにおいては致命的です。だから、太りやすくて、笑われやすい自分にはダンスは無理なのではないかと思っていました。でも、バーレスクは、体型も身長も人種も、そして笑われやすいかどうかも、一切関係なかった。そんなことよりも、「人とつながりたいという嘘のない心」が問われている場だということが魅力でしたね。
私が出会ったバーレスクダンサーの多くは「一番の欠点は一番の長所かもしれないし、一番の長所は一番の欠点かもしれない」というようなことを言います。まず、欠点をどう見せるかということです。見せ方によっては欠点が魅力になり長所になる。でも、欠点が長所になったとき、その長所に溺れるとまたそれは欠点になっていくのです。落語みたいですけどね。
photo | Shinsuke KOTANI

例えば私の場合、笑われやすいという欠点を、「ティーズ・オ・ラマ」で出会った老婦人は長所と思って帰ってくれました。それを意識しすぎてついつい笑いに走ろうとし、くどくなって長所が欠点に元の木阿弥、というお笑いの罠には何度も狙われました。普通のダンサーはそんなアホな事はないと思うのですが、こんなことがあるかも知れません。表情が上手なダンサーが、自らの表情を過信して、ナルシスティックに溺れる罠。ダンスのうまいダンサーが、踊りに固執することで、その人自身の本質ではなく「こんなにうまいでしょ」という自らの思いを見せてしまい、つまらなくなる罠。「私はこんなに音楽を知っている」「私はこんなに美しい」「私はこんなに努力している」―私は、私は、私は、となってしまうと、観客という相手が「想像力」を挟む余地がなくなってしまいます。それが長所が欠点になるときです。
想像力を挟む余地とは、例えばポーレの写真を見たときに、人は「このダンサーはどんな人なんだろう? どんな踊りをするのだろう?」と想像をかき立てられるでしょう。その「どんな」という部分が、絶対にはずせない面白みなのかもしれませんね。